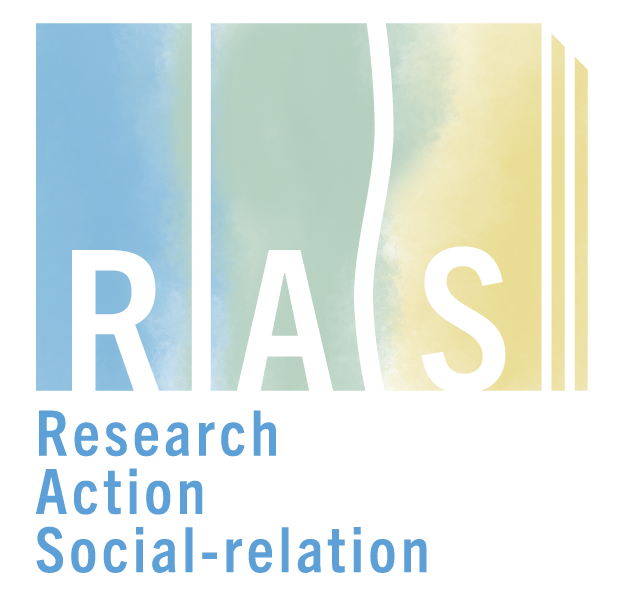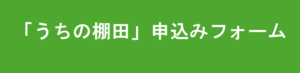日本の原風景といわれる棚田景観ですが、農家からすれば1枚1枚の面積が小さく形も不成形で大きな機械が入れられないため効率が悪い田んぼです。そのため年々耕作をする人が減少し、その景観はどんどん失われています。
NPO法人RAS研究会では、これまでうきは市のつづら棚田をお借りして共同で耕作を行う「棚田まなび隊」の活動を続けてきました。稲作や地域のことを学ぶ目的で、小さな機械で時間をかけて耕しています。この活動は同時に、棚田保全を目的として、都市民による通い耕作でどこまでお米作りができるのかという実験でもありました。
今年は、この棚田まなび隊に加えて、うきは市の分田地区の棚田で、それぞれが1枚の田を責任もって耕作する「うちの棚田」コースをスタートします。
自分で食べるお米を自分で作ってみたい、お米がどうやってできるのか知りたい、そんな方はぜひご参加ください。
ただし、利用するのは長く耕起されていなかった棚田です。そのため栽培にはかなり困難が伴うことが予想されます。まずは収量を目的とせず、稲作の技術を学んで、棚田保全に貢献する気持ちでご参加ください。
1年目の今年は来年以降の本格募集に向けたモニターとしての募集です。アンケート等にご協力いただきます。
場所:福岡県うきは市浮羽町新川分田地区
定員:3組(先着順)
料金:5,000円~8,000円(面積に応じる・モニター価格)
内容:1グループに1枚の棚田が貸与されます。管理は基本的にすべてご自身で行っていただき、収穫物はすべてお持ち帰りいただけます。
道具:農機具等はこちらで用意しています。長靴や軍手などはご準備ください。
時間:11時~15時(8月は10時~13時)
スケジュール(土曜か日曜の都合の良い方にご参加ください・応相談)
*うわ代かきのみ平日となります(5月22日)。
| 日程 | 内容 | |
|---|---|---|
| 第0回 | オンライン・応相談 | 説明会 |
| 第1回 | 4月12(土),13(日) | 座学・草刈り講習 |
| 第2回 | 4月26(土),27(日) | 田起こし |
| 第3回 | 5月5(土),11(日) | 荒代かき |
| 第4回 | 5月17(土),18(日) | 畦塗り |
| 第5回 | 5月22(木) | うわ代かき |
| 第6回 | 5月24(土)、25(日) | 田植え |
| 第7回 | 6月7(土)、8(日) | 草刈り・電柵設置 |
| 第8回 | 6月21(土)、22(日) | 草取り・草刈り |
| 第9回 | 7月5(土)、6(日) | 草取り・草刈り |
| 第10回 | 7月19(土)、20(日) | 草取り・草刈り |
| 第11回 | 8月9(土)、10(日) | 草取り・草刈り |
| 第12回 | 8月30(土)、31(日) | 草取り・しっかり草刈り |
| 第13回 | 9月13(土)、14(日) | 草取り・竹伐り出し |
| 第14回 | 9月27(土)、28(日) | 稲刈り・掛け干し |
| 第15回 | 10月11(土)、12(日) | 脱穀 |
| 第16回 | 10月26(日) | 収穫祭(まなび隊合同) |
Q&A
Q:収量はどのくらい見込めそうですか。
A:棚田の面積によりますが、小さな田で最大30kg程度、大きな田で50kg程度になります。ただし、病気や獣害によって収量がゼロになることも覚悟しておいてください。
Q:すべての会に参加する必要がありますか。
A:田植えまでの作業は重要なため、できるだけご参加ください。日程変更についてはご相談ください。
Q:1年間で稲作が学べますか。
A:棚田まなび隊では小さな機械を使って小さな田を耕作するやり方を続けています。大きな田は無理ですが、そのやり方での稲作を学ぶことができます。
Q:一般の田の耕作とどのような違いがありますか。
A:現在の稲作はほとんど大きな農業機械を使用しますが、私たちは基本的に手作業による昔ながらのやり方で耕作を行っています。ただ、利用できる機械は利用して負担を少なくしており、田起こしや代かきには管理機と呼ばれる小さな耕運機を使います。田植えや稲刈りはご希望に応じて手押しの機械をお貸しします。
Q:2年以上の継続は可能ですか。
A:近隣の棚田をご紹介しますので、ぜひ耕作を続けてください。「うちの棚田」に空きがあれば同じ場所での継続も可能です。
Q:小さな子供も参加できますか。
A:棚田は段差があり、また草刈り機など危険な道具も使いますので、言って聞かせられるくらいの年齢ならば可能かと思います。こちらでは責任を負いかねますので、保護者の方が決して目を離さず、責任をもってお連れください。

管理機を使って代かき

田植え

希望に応じて掛干しも